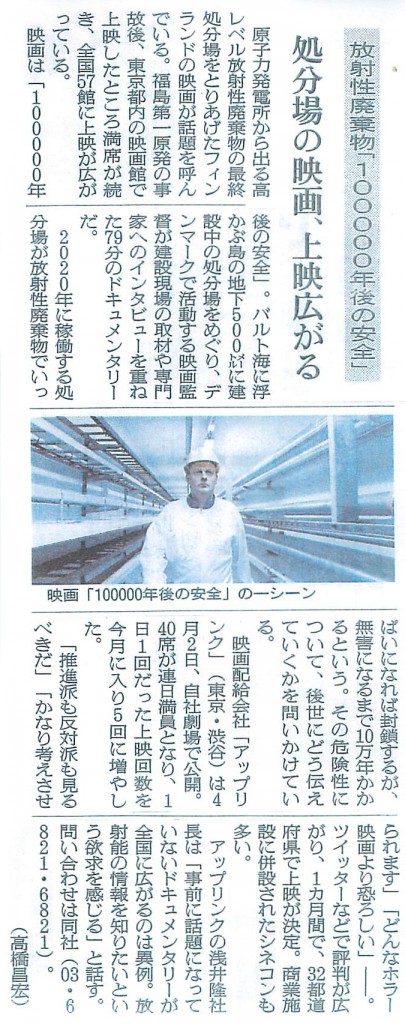上記のプログで下記請願が否決されたことを紹介した。
記
件名 一般質問に一問一答式の検討の件
要旨 一般質問に一問一答式の検討をもとめる。
理由 現在行われている朝霞市議会の本会議での一般質問は、
一括質問して、これに対応して一括回答されています。
他方、他の地方議会において近時、一問一答式を行うきころも
増えています。
ところで、現在の方式での一般質問にかかる時間は最大で約2時間
のようです。
そこで、一般質問の方式は、議員に委ねることにして、従前とおりの
方式で質問、再質問、再々質問各25分で行うか、もしくは試みに
一問一答式を例えば2時間以内で行うかを選択させるなどして、
一問一答式を検討して下さい。
上記のとおり請願します。
平成21年3月6日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日は会議録から討論を引用する。
◆19番(佐野昌夫議員)(民主党公認) 私は、平成21年請願第7号
一般質問に一問一答式
の検討の件について、本請願に反対の立場で討論をいたします。
議会事務局の調査によれば、一般質問には一問一答式を取り
入れている県内の市では40市の中で16市で、4割の議会が一問
一答式を取り入れていることがわかりました。逆に、40市の中で24市が、
およそ6割が取り入れていないこともわかりました。
請願には、ほかの地方議会においても昨今、一問一答式がふえている
ということですが、ふえているということを理由にして、この方式を検討する
ことについては、私は疑問を感じております。
現在の朝霞市の一般質問の方法には、これまで多くの先輩の時代から
培ってきた歴史もあります。現在の朝霞市には、朝霞市の考えがあっても
いいのではないでしょうか。そう思うのは、私だけではないと思います。
また、県内の他市の議会でも、6割が一問一答を取り入れていないことを
考えれば、私と同じ考えを持つ議員は他市にも多くいるのではないでしょうか。
しかし、私たちの議員の中にも、請願書に書かれていることと同じような考えを
お持ちの方もいらっしゃるのは事実でございます。
また、一般質問に一問一答式を取り入れている市の中でも、その方法には
さまざまであると聞いております。まだまだ研究の余地があると考えられます。
現在の方式は、私たちが長い間なれ親しんだ方法でもあります。本請願は、
一問一答式を行うところがふえているという理由で、一般質問の方式について
検討することを求めていますが、こういった理由で朝霞市議会の一般質問の
歴史を否定するものではなく、現在の方式も継続をしながらですね、
含め論議をすることが私は大事ではなかろうか、こう思います。
以上のことから、本請願に反対をいたします。
◆10番(小山香議員) 賛成の立場で討論させていただきます。
今の反対討論、二、三点要約しますと、議会改革の中でふえていると、
そのふえているという傾向を朝霞市で持ち込むのはどうかなと。
我々は、議会改革の中で議会活動をやっております。先進自治体、
その中でこの請願者は、今の朝霞の議会の運営方法、検討してほしいと、
ほかがふえているから、当然の請願の内容であります。
それから、大事なことは、一括方式から一問一答方式にふえている、
一問一答方式から一括方式に戻っていない。つまり、ふえていて戻っていない。
ということは、成果があるからじゃないでしょうか。
そして、諸先輩がつくった伝統、伝統にも守るべき伝統と改革しなければいけない
伝統とあると思います。この目線は、傍聴席で傍聴している方が、
今の方式でわからない。25分ぐらい前に言った質問、25分後の質問、20分以上も間あいている。
よっぽどのメモをとる人以外は、質問と答え、それわかりませんよ。
前もって議員が質問して、答弁書を作成して、その原稿を読んでいる当事者は、
それはわかるかもわかりません。原稿を持っていない人、それはわからないでしょう、
今何をやっているか、素朴な疑問じゃないですか。
そして、この請願で大事なところは、検討してください。先ほど、
反対討論の中で継続して、今の状態を継続しながら改革を図るべきだと、
まさしくこの請願は今の状態を選択して継続してください、現状を前提とした上で
検討してください、何ら現状のことについて一気に変えることを言っている
わけではありません、検討してくださいと。
したがって、こうした検討してほしいという請願までも否定することは、
全く市民にとってみたら悲しい意見じゃないでしょうか。そういった意味では、
我々議員が市民の目線に立った議会活動をするために検討を求める請願、
極めて妥当なものであり、賛成といたします。
◆1番(斉藤弘道議員)(共産党) 私は、この請願第7号に賛成の立場で討論したい
と思います。
今、新しい取り組みとして、多くの市議会でこの一問一答式による一般質問の
導入の取り組みが始まっています。私たち朝霞市議会の場合は、長く一括質問、
一括答弁で3回までという方式を続けてきました。その3回の中で、
我々議員は実態を明らかにさせ、またその中にどんな問題があるのか、
そしてその問題の本質がどこにあるのか、そして最後にはその解決方法や
目指すべき方向がどこにあるのかを、この3回の組み立ての中で苦心をしながら、
いろいろな答弁を引き出しながら取り組んできました。これはこれで、
私は一つの方法だと思っていますけれども、一方で先ほども出ていましたけれども、
多岐にわたる、何項目にもわたる、私なんか大体3項目から5項目か
そのぐらいですけれども、多い人は7項目、8項目、10項目という項目を
1回の質問の中でして、またそれに対する答弁が返ってきてということでは
わかりにくい。先ほど、前者の討論にもあったように、わかりにくいという面もある
と思います。
一方、一問一答式は、すぐ質問をして、それに対してすぐ答えが返って
くるわけですから、わかりやすいという面と、同時にその一つ一つのことが
1回の質問で、例えば思うように答えが返ってこないだとか、違う視点から答えが
返ってきたときに、その問題にとらわれてしまって、なかなか3回の中で組み立てを立てて、
最後の本質の部分、改善の部分までいかなくなってしまうというおそれもないわけではない
と思っています。どちらにしても、一長一短はあるんだと思います。
そうした中で、我々議会の一般質問が住民のための役に立ち、
議論がより豊かになり、よりわかりやすくしていくという改革は、
我々議員は常に住民から求められているというふうに思っています。
本請願は、選択制も含めて一問一答式を検討してほしいというものであり
、一問一答の採用を押しつけるものでもなければ、この請願を採択したからといって
決定づけるものではありません。
そういう意味では、先ほど反対討論をされた方の危惧というのは、
これは当たらないというふうに思います。既に、この請願の検討を通じて、
先ほど委員長報告がありましたけれども、十分皆さんに伝わったかわかりませんけれども、
ある意味この一問一答式の採用の検討について議論を、まだまだ緒についたところですけれども、
始めてきました。ぜひ、引き続きこの請願を採択して、どういう方向がよりよい方向なのか
検討していきたいというふうに思っていますので、ぜひこの請願に賛同していただき、
採択していただきたいということを申し上げて、賛成の討論といたします。
◆5番(田辺淳議員)(市民ネット) 私も、この請願に賛成の立場で討論しますけれども、
民主党さんで議会改革を訴えながら選挙をやられたという、
そういう方もこういう、言ったというふうに思っていますけれども、
改革という言葉はいろいろとあって、中身がやはり問題だというふうに
私は思いますので、その改革のあり方というのはやっぱり本当にみんなで議論しながらやっていくと。
ただ、議会も今まで、この部屋の中で比較的密室状態、ようやくモニターが朝霞市はついて、
外にもその状況が伝わるようになりましたし、また方法的にも少しずつ改善されてきている
ということで、市民のやはり関心もどんどん高まってきているというふうに、
そういう中で議会の改革の請願というのは、本当にここにきてこの数年、特異な請願だと思うんです。
今まで、その以前、私も20年以上議員やっていますけれども、議会改革に絡む
請願というのは今までほとんど全くなかった。それがこの数年の中で、議会改革絡みの
請願が出てきているというのは特異な状況だというふうに思うんですけれども、
それだけ市民の関心が高まりつつあるということは、もう間違いないというふうに思うんですね。
やはり一般質問に関して、私の長い経験の中では、むしろ議会のルールとして
回数制限というものがあって、時間制限があるという、そういう枠組みをむしろ短くしようと、
あるいは回数も狭めようと、少なくしようというような、どちらかというと執行部をおもんぱかる、
そういった議論のほうが大勢を占めているという傾向があったという中で、私どもはどちらかというと、
むしろ守勢に回って、議会で今までやれていたこと、それを既得権を守るという立場に立たざるを
得ないことが多かったと。
ところが、市民が市民の目線で客観的にながめると、もっと素朴なところでですね、
一問一答と、何でやっていないんだというのは、それはもうもっともなことであって、
これは委員会ではもう朝霞市でもずっと一問一答をやっていますし、時間制限もなく質疑ができると、
同じようなことをここでやるのが一番自然体だと思います。それはそうだと思いますけれども、
そこに時間の枠をつくり、あるいはその人間が何回質問ができるという、そういう枠をつくってきたのは、
それはやはり執行者がそれに対して応じるということも含めてですね、
むしろ執行者をおもんぱかったがゆえの仕組みが今までずっと維持されてきたんだということを
やはり私ら率直に受けとめるべきだというふうに思います。
やはりこれから先、今はまだまだ、それでも議会改革を求める声というのがそんなに
強いかどうか私らはわからない。アンケートで、議会がもっと率直に市民にアンケートでもとって
、議会に対してどういう思いがあるのかというのを、やはり朝霞市議会として市民の目線、
ちゃんと立っていくということがこれから求められているんだと思うんですね。
その一つとして、私客観的に確かに傍聴する立場でいうならば、質問して、
その質問にすぐ答えが返ってくるというこの形は、私は一番自然だと、回数制限をまず、
つまり質問の回数制限をなくすということだと思うんですね。
ただ、それと引きかえに、例えばそれを時間制限をつけましょうということで、
取引のような形になるのはやはり私は違うんではないかという立場はとって、
今までもいるんですけれども、やはりある程度のルールはもちろん必要だ
と思うんですけれども、そういったところ。
あとは、現実的にここで、この本会議場で一問一答のやり方をするのに、ここで立って起立をして
、一々質問をする、答弁をするたびに立って座ってというのをこの場でやるのか、
演壇でやるのか、答弁の方は演壇に行くのか、この状態で答弁をするのかという、
そういうことを技術的なことも、物理的なことを考えたときには、
恐らくこの議場自体の形自体も変えなければいけないことにも通じると思いますので、
そんなにすぐにね、すぐにやろうとすれば、この場で立ち上がって、あるいは座ったまま質問をし続けると
、一問一答を繰り返すという形で現実的にはできないことはないでしょうけれども、
そういった技術的な問題も含めて検討の段階には入っているというのは間違いないと。
私は、そういうことも含めて、検討をするということは、何ら私は皆さんも別に検討すること
自体を否定するものではないと思うんですけれども、それを否定をする、それを否決をするというのは、
やはりこれはもう本当に昔からの朝霞市の議会の悪いところであって、
決して内容的におかしくないものであっても、皆さんが恐らく賛同するであろう表現であっても
否決をして、またそれを議会改革自体は多分否定されるものではない
と思うんですけれども、進めようという、そういうやり方はやはり非常にわかりにくいし、
傍聴者もいらっしゃると、そういう中では今後はやっぱりやめていただきたい
と申し上げながら、賛成討論といたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
市民の想定外の秘密投票で行われたが、
賛成及び反対は、下記のとおりであると推察されている。
賛成
11
公明党(5名中3人A、B、C)
共産党(3人)
市民ネット(2人)
無所属(3人)
反対
12
進政会(7人)
明政会(3人)
公明党(5名中2人D、E)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当初一般質問に一問一答式について
市民ネットは質問(25分)再質問(25分)再々質問(25分)の既得権が
奪われると言って反対していた。
最後は上記の通り、賛成された。
ところで請願は、既得権に配慮し、選択制かつさらに検討という
議員各位に配慮したものである。
これなら反対する理由などはない筈である。
しかしながら、上記のとおり
反対者ありしかも多数であった。