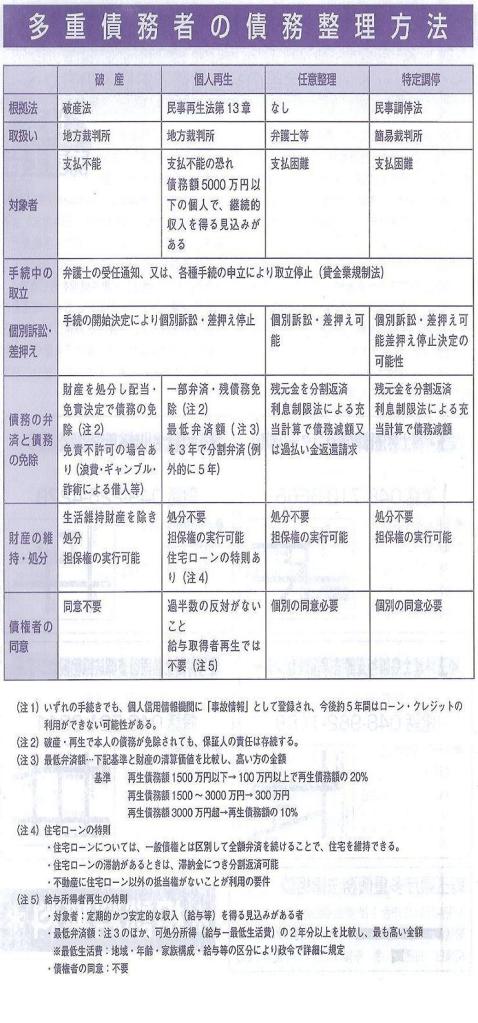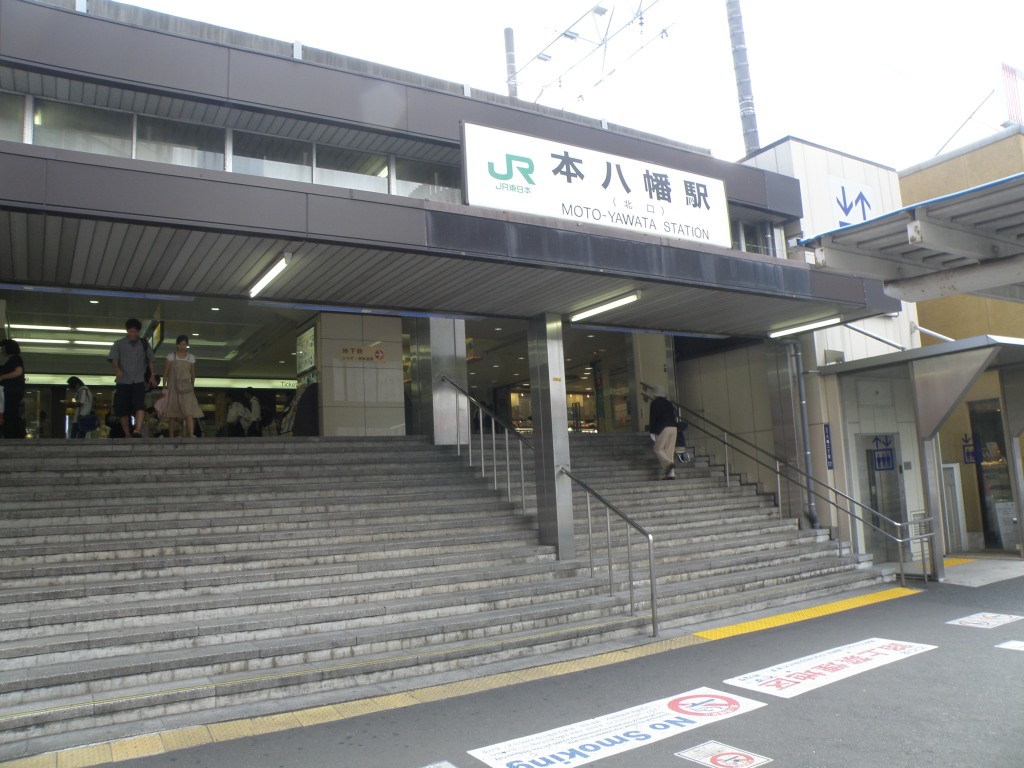先週の土曜日、桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学法学部校舎で
同大学のミディエイション交渉研究所公開研究会で以下の
要旨で報告をした。

報告名は「法的対話型紛争解決としての労働審判制度」
である。
1 問題の提起
平成18年4月1日施行の労働審判制度の解決率は約8割である。
この解決率8割の要因は何であろうか。
(大幅に中略)
2 法的対話型紛争解決としての労働審判制度
労働審判制度における法的対話は、全部白紙にできるという制度設計によって支えら
れている。当事者に本音の発言をする機会をあたえ、どんな不利益なことを発言しよう
とも、この発言は審判に対する異議による訴訟に引き継がれない。
一見危うい制度の外見を呈しながら、当事者は、自分の意思でこの制度を利用して合
意したとの確信に至るのである 成功率8割は、上記のような法的対話の成果である。
・・・・・・・
コミニケーション能力の不足が私たちの社会において問題になっている。
労働審判制度は、一つの解決策を示唆しているようだ。
当事者は、対話のルールを身につけている。
当事者には、十分な発言する機会がある。
審判員は、労使の労働慣行を熟知しており、その助言は
裁判官の抽象的な助言よりも、現場の生きた助言であり、
説得力がある。
当事者に特段の圧力を加えない。
よって、当事者が自由に、解決策を選択することができる。
その選択が合理的になされ、約8割が一致しているということだ。
・・・・・・・
なお、他の報告者は「小学校における紛争解決に関する学習指導についての
研究ー「交渉」の手法を用いてー」を行った。
この報告がなされた小学校は埼玉弁護士会が行っている法教育の
実践の学校であり、この報告書には昨年度の法教育に協力をしてもらった。
・・・・・・
ところで、埼玉弁護士会の法教育は、上記研究所の下記理念を
取り入れている。
記
争いという緊張度の高い衝突の場において、
当事者の話によく耳を傾け(傾聴)、
争いの根底にあるものを深く掘り下げ、
広い社会的な文脈でこれを捉え直し、
人間関係のより高次の調和につなげる
・・・・・・
現代社会で争いの典型は、イスラエルとパレスティナであろうか。
争いの根底になにがあるのだろうか。
この争いの根底にあるものを大きな社会関係で
捉え直すとどのようになるのだろうか。
そして、イスラエルとバレスティナとの間で
調和すなわち、平和は実現できるのだろうか。
・・・・・・
私は、今回の報告をする過程で、
上記研究所の所長が主張されている
「法的対話論」から
「法的対話理論」へ
さらには「法的対話権」に
発展させたいと思っている。
それは、上記のイスラエルとバレスティナの
和平への途を念じているからである。
・・・・・・・
日本国憲法の平和的生存権は、日本国憲法固有の
権利ではない。
日本国憲法が人権理念として、平和的生存権を発見したのである。
平和的生存権が人類の普遍的な人権として存在しているのである。
そうだとするならば、人類の究極の目的があるいは原理的な理念が
平和的生存権であるということは、
平和的生存を希求するために法的対話権が存在している
のである。
そして、市民法の起点に法的対話理論が存在している。
国民主権は、国家を介した国民相互の法的対話権である。
・・・・・・・
埼玉弁護士会の法教育はユニークであり、他に例をみない。
これまでの法教育は、模擬裁判とか、机上の問題を解決するルールづくり
が一般である。
これに対し埼玉弁護士会では、身近な紛争を解決する手法を
学ぶ法教育である。
すなわち、この法教育でもとに生きるための知恵を学ぶことを
目的としている。
実は、法は人類が生んだ、人間が共に生きるための知恵なので
ある。私たちは法の理念を進化させ、法が人間が共に生きるため
文字通りの知恵とあることを願っている。
・・・・・・・
上記大学の学長は、私の恩師である。恩師から考え方の相対性を
学んだ。
また、上記交渉研究所の所長も 学長を恩師とされている。
私たちは、いわば同門の学徒である。
この恩師のもとで法学入門を学んだこと。
これが現在の私の原点の一つであることは間違いのないことだ。
上記研究所から報告の機会を与えられ、報告を通じて
人権問題にさらなる勇気をもらった。
大変に、いい機会を頂いたと思っている。