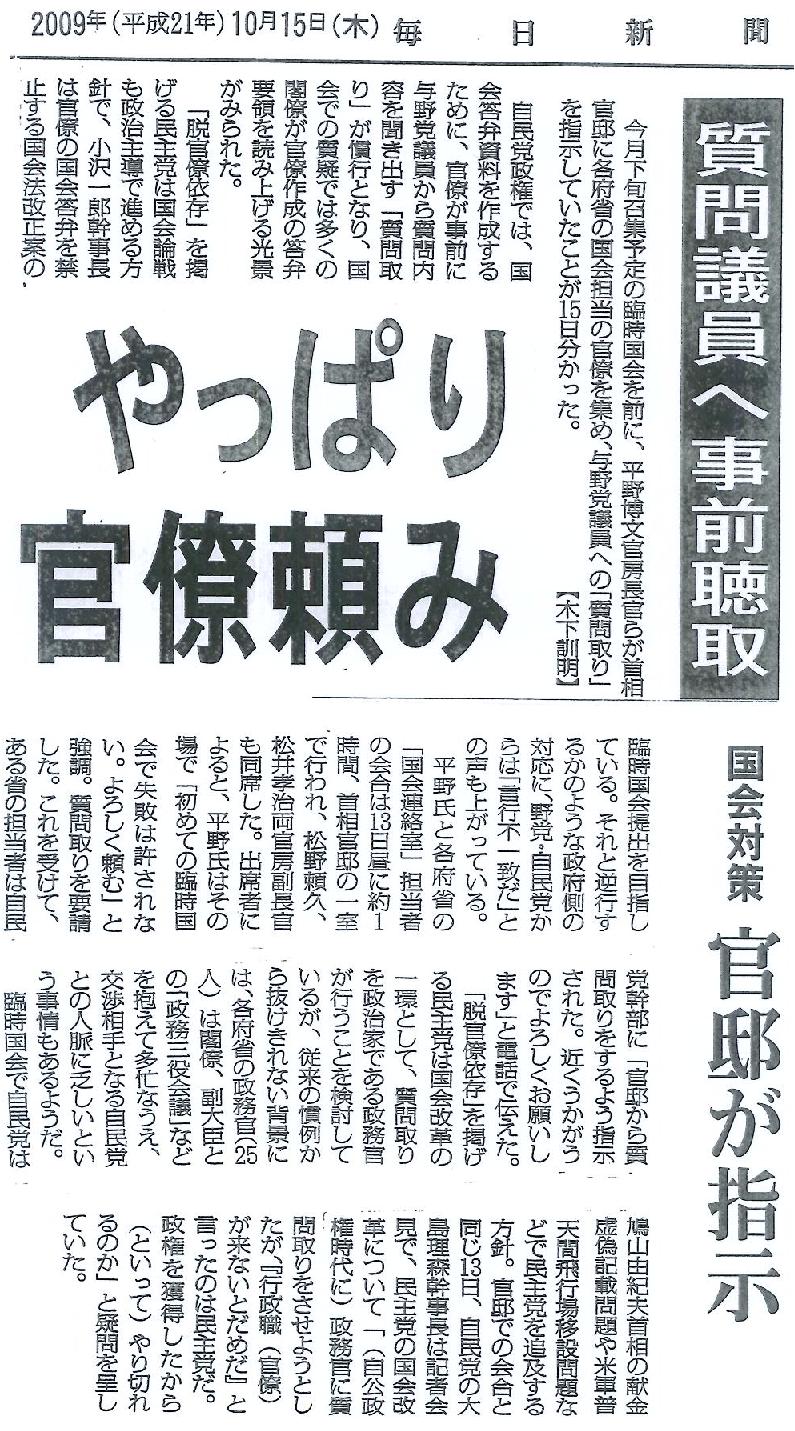Posted on
2009年11月18日 by 小山 香, under
日々思うこと,
議員活動
昨日、全員協議会の後、代表者会議があった。
12月の定例議会の段取りの話し合いかあった。
議長から公務員の賃金がカットされていることに関連して
地方議会の議員の報酬も減額すべきかどうかの
提案があった。
これに対し
・ 朝霞市は議員報酬が低すぎる。
・ 定数を28人から24人と4人減数という痛みを行った。
・ 矢祭村では議員報酬日当制としたが、これは問題で、議員を専業に
している人は生活できない。
と否定的な意見が続いた。
ところで、6月の定例会において市のの職員の報酬の
減額条例について市の職員は、だれも反対しなかった。
そこで、私は減額条例に賛成した。
しかしながら、議員の減額について、議員の生活に
関することなので、まずは、報酬減額については、
全員で自由討論で議論をし、全会一致を目指すべきと話した。
・・・
論点は、朝霞市の議員報酬は、他の自治体に比べて低い。
だからこれ以上の減額は無理と解すべきか。
それとも、仮に他の自治体に比べて低いとしても
現に市の職員が報酬減額の痛みを受けており、
市議会議員も同様に痛みを分かち合うべきか、どうかである。
・・・・・
ところで、議員報酬は、進む方向としては、
議会の土日・夜間開催を条件の、兼職を前提に、
ボランティアでよいのではないか。
Posted on
2009年11月17日 by 小山 香, under
日々思うこと,
貧困と人権
先日の人権大会で学んだことを以下のとおりまとめた。
すこし誇大気味?になってしまった。
1 人権は、価値判断である。人間には当然に尊厳をもって生きる権
利があることと決めたのである。
人間の理性として、生命を大切にするとういう約束事である。
ところで、人間は等しく 人権を認めることにしたが、特に女性、子ど
も、高齢者、障がいのある人などは、その人権を自ら守ることが困
難であり、差別,虐待、陰湿ないじめな受けやすい。
だから、人権の被害を受けやすい人たちに対し特別に保護をしな
ければならないのである。
2 人権は民主主義社会の存続と発達の基盤である。
人権の擁護が最初にあって、公共の福祉の維持がある。
だから、人権の尊重は、社会の起点である。
3 在野の法曹の弁護士は、在朝の役人と違って、
あるいは象牙の学者と違って
市民社会の具体的な事案と具体的な人々の中で活動している。
人々の心の痛みとか、悩みとか一番知っている。
したがって、議論が浮つくことはない。
4 また、同人がもっている法や制定法についての
知識や理念を一般の人が理解できるようなに啓蒙する。
よって、市民社会で法の理念が共有される努力をする。
5 さらに 「社会は、より良い社会に変えられる」という信念を
もって表現の自由を行使する。
またさらに、市民に対し積極的に助言を行って、
単なる知識ではなく市民の「生きる力」を引出し、
もしくは「生きる力」を支える。
なお、表現の自由民主主義社会の根幹であることは
自明の理である。
人間に思想の自由があって、
人間は自律的に判断能力できるという
信頼の背景があって、表現の自由が全うできるのである。
6 日常の小さな問題から
より大きな問題まで
そして今世界が直面している困難な問題も
新たな解決策を探り、 見いだして、
解決するのを助けるのである。
7 在野の法曹の弁護士は、以上のような課題と
果たすべき役割をもって活動しなければならない。
すなわち、
本当に大事なことを真摯に提言して
権利を実現し、あるいは権利の実現のために
場合によったら、法律の矛盾を指摘し、
立法も提言する。
このようにして
すべての人のために
市民社会の持続可能な発展の達成に寄与するものである。
・・・・・
なにか宮沢賢治の「アメニモマケズ」みたいな表現に
なってしまった。
Posted on
2009年11月14日 by 小山 香, under
日々思うこと,
貧困と人権
先日、ある市の福祉事務所の生活保護申請に同行した。
同行しなければ、すでに一度福祉事務所に訪れ、職員のこれでの態様から、
生活保護の申請をさせないと思ったからである。

文書を作成、有無をいわせず、
申請した。受理された。
しかし、おそらく、
今度も申請者一人で行ったら、
当局のいう「相談」でおしまいにされたろう。
母子家庭で、高校生以下の子4人がいる。
収入はパート収入だけである。
以前正社員時代にマンションを購入し、ローンを抱えている。
子どもの養育の関係で、正社員を断念せざるを得なかった。
ローン、サラ金の借金がある。
しかし、生活困窮者であることは明らかであった。
しかしながら、生活保護の途は遠かった。
申請者は、私の前に法テラスに相談に行った。
相談した弁護士から具体的な解決策の提案は
なかったようだ。
私も、最近までは、生活保護の知識はなく、
行政の言うままだった。
例えば
住民票がない。
親兄弟にまず頼みなさい。
自動車を処分しなさい。
サラ金の借金があるとだめです。
住宅ローンがあるとだめです。
私は、サラ金と住宅ローンで申請を体よく
拒否されると思った。
しかしながら生活が困窮しており、放置ができない。
緊急性があり、平日休んで私の所に相談に
来ると、パートの収入が減るので
休日に来てもらい、
私も直ちに生活保護申請の同行をすることにした。
大きな論点は2と他に1つある。
1 マンションに住み、ローンを抱えている。
2 サラ金かの借金がある。
3 高校1年生の子がいる。
上記1について、
競売でマンションは処分される。
上記2について
私が整理する。
上記3について
生業資金として
アルバイトを強要せず保護してもらいたい。
担当者は納得した様だ。
いつも感じる。
このような場合
弁護士とか
市議会議員が同行すると
生活保護は動く。
そんな人に出会わなかった
場合、どんなことになるのだろうか。
話は飛躍するが
あの連続殺人永山則夫に
生活保護の手が差しのべられて
いたらと思うことがある。
どんな状況でも、生存を守るのが
憲法25条であり、生活保護法だ。
Posted on
2009年11月12日 by 小山 香, under
日々思うこと,
議員活動
下記のとおり父子手当の立法化されるという。

朝霞市議会の平成20年の6月議会で父子手当条例の請願が可決され
また、国に対する法律改正の意見書が採択された。
この記事をご覧になった新座の一人親会の福田さんが
父子手当て条例を近隣四市さらには埼玉県全市町村に
広げたいと尽力されていた。
この活動の影響を受けたものと思いたいが、
参議院議員の島田議員が先の参議院予算委員会で
取り上げ、上記のとおり、鳩山首相が述べたと思っている。
一人一人の力は小さいが、それが連携して、
大きな力になったものだ。
いずれにしても
原点は朝霞市議会
の平成20年6月議会の
議決である。
賛成された
公明党5名
共産党3名
市民ネット2名
無所属3名
合計13名が
児童扶養手当法の改正の
原動力の起点である。
Posted on
2009年11月8日 by 小山 香, under
日々思うこと,
貧困と人権
下記の貧困ビジネスがやっと白日に曝された。

これまで、問題にされてきたが、行政は黙認していた感があった。
やっと、貧困ビジネスに対し行政が動き出した。
土曜日、貧困ビジネスの寮にいる人たちの
相談会があった。
3条の部屋をベニアで仕切り、二人部屋とし、
これで一人4万7000円の二人合計9万4000円部屋代を徴収し、
朝、味噌汁もない弁当、夜も弁当、宿泊者の当事者いわく、
朝、晩2食の合計400円くらいという。
お風呂とか、洗濯機はあるが、約5万円位とられるという。
県の担当者が視察にくるときは、ベニアをとって、
一人部屋にするそうだ。
生活保護費約13万円から約10万円を宿泊費として
徴収するのである。
残り3万円では、ここから脱出することは困難である。
そこで、私たち法律家が、この宿泊所から、アパートへの
転居の生活保護申請の同行をするのである。
当日、上記の様な寮から抜け出て、
やっと自炊でき健康的な暮らしが
出来るようになったと報告されたひともいた。
少しずつであるが、
私たちは、上記の人たちにアパート暮らしができる
ように活動を始めたのである。
憲法13条の人間の尊厳
憲法25条の生存権
の問題だ。
Posted on
2009年11月7日 by 小山 香, under
日々思うこと,
貧困と人権
11月5日、6日と和歌山で人権大会があった。
5日には次の分科会があった。
1 今表現の自由と知る権利を考える
ー自由で民主的な社会を築くためにー
2 ストップ地球温暖化
ーHOTな心でCOOLな選択をー
3 安全で公正な社会を消費者の力で実現しよう
ー消費者市民社会の確立をめざしてー
私はこの分科会に参加した。
消費者市民、労働者市民、そして生産者市民
市民社会の市民が共生する社会を目指したい。
人権大会にくると日々人権に関わっている弁護士から刺激を受ける。
6日は分科会の報告を踏まえ、大会決議をする。

上記は6日の日弁連の大会の様子
手話通訳が写真左の様に入る。
文字反訳が写真右に様に入る。
このように人権に配慮している。
壇上右に来賓の席があるが壇上には
国会議員の席はない。
最高栽長官、検事総長、法務大臣、和歌山県知事、和歌山市長である。
国会議員がきた場合、檀下の前席である。
在野法曹の理念を貫いている。
・・・・・・・
地方都市を訪れると時間がゆっくり回っていることを実感する。
都会でせわしくしている私たちとリズムが一致しない。
このような地方都市で生活して、たまに都会に出る生活の方が
都会に夢があっていいかも知れない。
(私も当初の予定通り、郷里に帰ったいたら、・・・・・)
いずれにしても、この大会で得たものは大きい。
さらに日常活動でも生かしたい。
Posted on
2009年11月3日 by 小山 香, under
教育,
日々思うこと
11月1日、韓国の慶州で埼玉・仁川弁護士会セミナーに出かけた。

韓国側の提案の
「ロースクール問題について」
韓国では、今年からロースククールが始まる。
日本2004年から始まっており、日本のロー
スクール問題を学びたいというものだ。
次に
日本側の提案の
「法曹人口問題について」
韓国では一足先に急激に激増させた。
韓国側にどのような問題があるか。
知りたいからだ。
・・・・・・
ところで、韓国では日本統治下に日本の司法に組み込まれた
経緯があり、大抵に議論は、法律の定義が同一であり、容易に
理解できる。
日本のロースクールは学費がいるが、韓国ではいらないそうだ。
日本で、貧困者の子どもは、法曹になることが困難になっている。
貧困から、社会の不合理に目覚めて、法曹になりたいと思う人は
出てこなくなるのではないだろうか。
Posted on
2009年10月30日 by 小山 香, under
日々思うこと,
貧困と人権
日本では刑罰厳罰化が進んでいる。
先日、日弁連で講演会があった。
刑罰寛大化?の国ーフィンランド

フィンランドの刑事司法
1 フィンランドでは最後の死刑が約140年前です。
2 終身刑はありますが、最長19年で仮釈放されます。
要するに、矯正不可能という人はいないということです。
3 窃盗については日本では常習ということでは3年になってしまいますが、
フィンランドでは3カ月です。
4 懲役8か月迄の実刑判決は、社会奉仕命令の代替する。
社会奉仕の1時間は刑期1日に換算する。
5 4~8か月の実刑は電子監視に変える。
6 フィンランドでは刑務所に塀がなく、懲役で仕事する人は
月14万円の給料をもらい自分で食事を作るか、
刑務所の食堂でお金を払って食べるか、自由ということです。
7 スオメンリンナ開放刑務所の紹介がありましたが、
軽井沢の別荘のようで、サウナもあります。
部屋は我が家よりも快適な感じです。
8 厳罰化を求める政治家も市民もいない。
9 なぜこうした政策がとられるかというと、
社会に出して普通の社会人として生活させるためには、
懲役は刑罰というより社会復帰のトレーニングの場と
考えているからです。
いずれにしても、聞くことすべてわが国では想像外の
囚人に対する心温かい政策です。
私は次のような質問をしました。
Q:フィンランドではホームレスについては
国の責任だと伺ったことがあります。
犯罪もフィンランドでは国の責任だ
と考えてこのような政策をとっているのでしょうか。
A:国家に責任があるとは言っていませんでしたが、
犯罪は犯罪者一人の責任ではなく、
社会にも責任あり、その一人だけに
負わせるべきではないと至るところで言っておりました。
いずれにしても、フィンランドの人に対する深い思いの
政策について考えるところ大であります。
フィンランドの刑事司法の現状は、
文字通り、人間讃歌の国であることは間違いが
ない。
日本の刑罰は悲惨だ。
まず、丸坊主になる。
ねずみ色のいわゆる囚人服をきる。
歩くとき、手を肩まで挙げて歩く。
休憩時間以外横を向いたり、
人に話しかけてはいけません。
警務官に口答えをしてはいけない。
口答えすると懲罰にかけられ、
劣悪な独房に入れられます。
要するに
人間から自尊心を奪い、
無批判的に権威に従わせます。
ある人が刑務所の施設をみて
犬小屋だ。
直視できないといっていた。
これに対し
フィンランドの刑務所は
光が注ぐ、モダン建築の様相である。
ここなら、人間性を回復し社会復帰すると思う。
日本の刑務所は、
陰惨な風景であり、
人間性が喪失すると思う。
環境が人間性を育むことの実証だ。
Posted on
2009年10月18日 by 小山 香, under
日々思うこと,
議員活動
しばしば発言していることだが、
地方議会は二元代表制といわれながら、
なぜ、議員提出条例がないのか。
ところで私が議員になった平成19年12月
の初めての定例会に住民投票条例案という
特殊の手続条例が提出されたことがあった。
私は、これからは、福祉とかまちづくりとか
条例案がバンバン提出されるものと思った。
しかし、未だない。
事務局に聞いたら、そのような条例を提出した
ことはないといいていた。
これに関連して、すこし前の議院運営委員会である会派
の議員が、ある請願書の文言中に
「議会は執行部の諮問機関としての面があるとしても・・・・」
の諮問の表現は納得できないと主張されていた。
このままでは、この請願は、我が会派は賛成できない
と発言されていた。
当該議員としては、議員の誇りを傷つけるもので
あるという、ひとつの見解である。
ところで、先日紹介した片山前鳥取県知事の
講演(地方議会は「八百長と学芸会」である。)
には、次の発言がある。
記
議会のMISSION(使命)でもう一つ大事なのは
「立法」地方議会だと条例を作ることだが、
恐らく多くの地方議会では「立法」していないのではないか。
(市町村の)執行部が作った条例案に対して「うん」と言うか、
文句を付けるか、揚げ足をとるか。
よく議員の報酬が高いか安いかを聞かれることはあるが、
それは見方による。
きちんと立法してくれる議員なら安いものだろうし、
執行部の出したものに「うん」と言うか「けち」をつける
しかしないとすれば、こんなに高くつくものはない。
議会は「立法機関」であるはずなのに、
立法機能をほとんど執行部に丸投げしてしまっている。
アメリカでは市町村長に、立法の機能がない。
法律等は全て議員立法になっており、
首長が「こういう法律が必要だ」と思ったら、
議員に頼んで作ってもらうぐらいだ。
自分が知事の時、議会が条例を作らないものだから、
代わって執行部が作ってあげてたので
「可決」しても頭を下げなかったら、
「通してやったのだから頭を下げろ」と文句を言ってくる人が
いたくらいだが、見当違いも甚だしい。
もう一つは「チェック機能」だ。
予算の執行でも、教育委員会の人事でも、
それが適切に行われているかどうかを
市民になりかわってチェックするのが議会の重要な
使命なはずだが、これがなかなか機能しない。
「人を疑ってかかるのはどうも・・」という「人のよい」
議員さんが多すぎるからだ。
しかし、それでは「品質管理」ができない。
絶えずチェックをしておかなければ「権力」というものは
「暴走」あるいは「腐敗」してしまうかもしれない。
だから議員は、常に「疑いの目」で権力をチェック
しておかねければならない。
人を疑ってかかるのは誰しもいやなものだ、
しかし、人のいやがることをするからこそ、
安くない報酬をいただいているのではないか。
「人を疑ってかかるのはいやだからチェックできません」
というのであれば、議員の報酬は返上するしかない。
・・・・・・
朝霞市議会はどうであろうか。
議案審議のとき、
反対討論のあと
賛成討論をすることになっている。
執行部提案の議案に対し
反対の討論があると
大きな会派の議員らは、どこからか原稿を
出してきて
執行部提案に対し
格調高い賛成討論をする。
日頃そのような発言をしたことのない議員が
原稿を手に発言している。
あるとき
「こくみん みなほけん・・」と原稿を読んでいた。
私たちは、文脈から「国民皆保険」と理解した。
賛成討論の原稿は誰が書いているのだろうか。
国会の様に議院内閣制なら
官僚の賛成討論の原稿依頼はありうるが、
二元代表制度の地方議会で議員の
賛成討論の原稿を朝霞市の職員が作成しているとしたら
脱「諮問議会?」どころではない。
議員のプライド、倫理に抵触する。
(もし職員が、議員のために原稿を作っているとしたら
内心軽蔑していないだろうか.)
のみならず、議会の自己否定行為では
ないだろうか。
私は、地方議会が諮問議会から脱却し、
文字通り議案を提出する議会であることを
願って活動をしているもののひとりでありたい。
Posted on
2009年10月16日 by 小山 香, under
日々思うこと,
議員活動
国会でも、官僚が大臣の答弁を作ってくれるということだ。
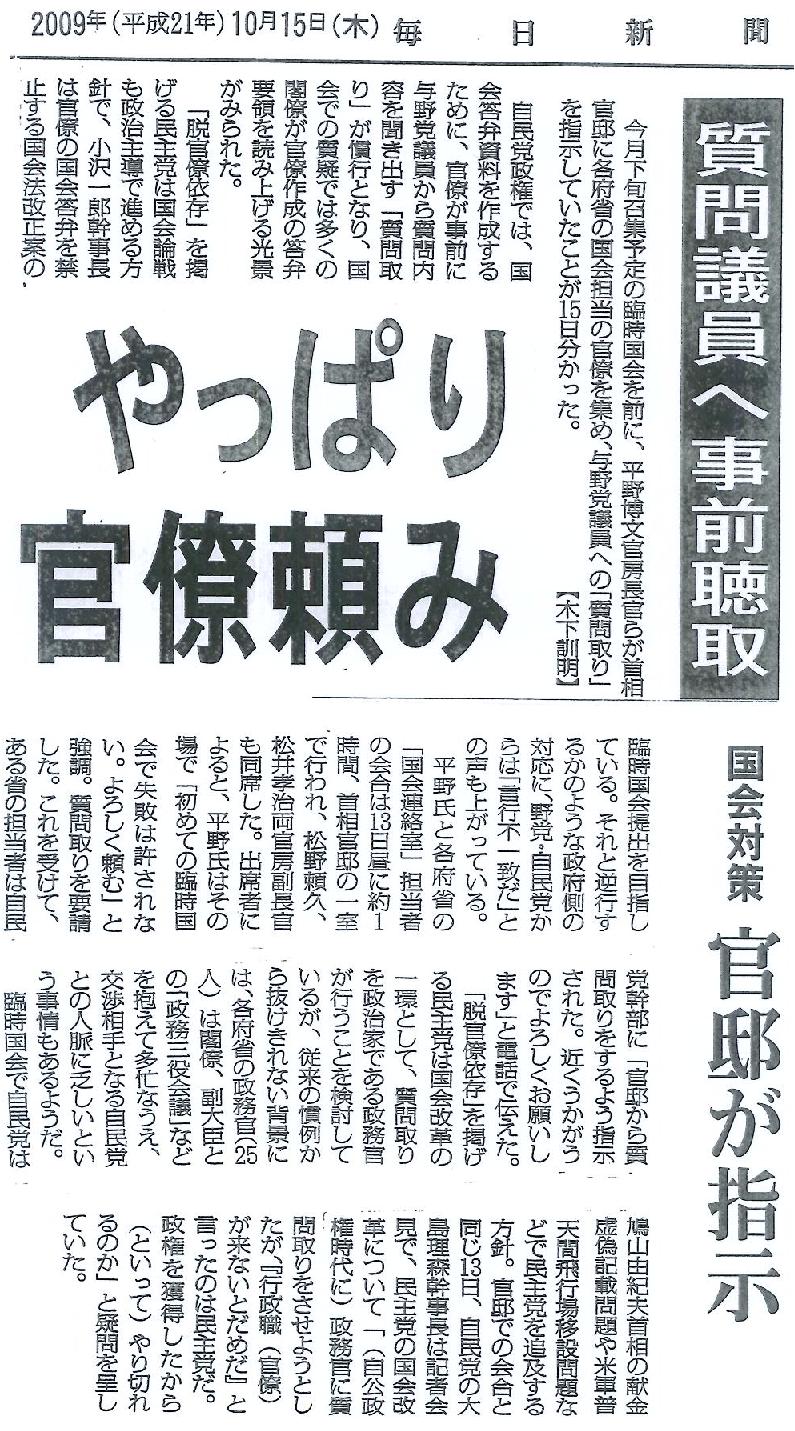
それでも、予算委員会なんかには、緊迫感がある。
予算委員会は、一問一答式である。
しかし市議会には緊迫感がない。
その原因は、市議会は、一括質問・回答式に問題がある。
すなわち
一括質問・回答式で質問取りがあると
市議会には緊迫感がなくなる。
例えば、朝霞市議会では
質問25分
回答(市側)
再質問25分
回答(市側)
再々質問25分
回答(市側)
質問も回答も一括方式でやるのである。
(ところで、今市議会に一問一答式の導入を検討してほしい旨の
請願が出されている。これは緊張感ある市議会を目指すものだ。
全会派、当然に賛成されると思ったが、
そうではない。)
・・・・・・
地方議会の「質問取り」について元鳥取県知事の
片山氏が次のように言っている。
(片山前鳥取県知事 講演要旨抜粋)
地方議会を全て観て回ったわけではないので、断定はできないが、
その現状は「かなりひどい」と言って差し支えない。
議会は何のためにあるのか、そして、誰のために仕事をするのか、
ということを忘れているの地方議会、特に都道府県議会で顕著だが、
多くの議会では「八百長」と「学芸会」をやっている。
「八百長」というのは、「結論」がすでに決まっているということだ。
「学芸会」というのは、シナリオ通りセリフが決まっているということだ。
質問も答弁も、再質問すらも原稿ができている。
議員も執行部もそれを読むだけ。
そういう意味では、セリフすら覚えていないから、
「学芸会以下」と言ってもよいかもしれない。
(なお、片山氏は北海道議会が、八百長」と「学芸会」の典型と発言
したところ、北海道議会から抗議を受けた。)
・・・・・・・
朝霞市議会はどうであろうか。
弁護士の会合である市の弁護出身の市長は
一切原稿無しに六法全書だけで答弁していたそうだ。
真相を確かめたいと思っている。
(なお、私は原則として原稿を読み上げずに、
質問では議員のみなさんと傍聴されている方々に
再質問、再々質問では、市長等の執行部のみなさんの
お顔をf見ながら質問をしている。)